
原作 羅貫中『三国志演義』 作・絵 彩ますみ
【13】 関羽、青龍偃月刀を授かる
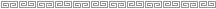 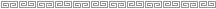 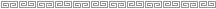 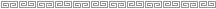
そして、関羽の十八歳の誕生日である、六月二十四日の前日の晩。
その日の夜は、偃月(えんげつ)。
すなわち、美しい三日月であった。
ふくろうの声が夜の闇にこだましている。
塩密売の稼業を終え、眠りに付く関羽を、低い声が静かに呼ぶ。
「……これ、関羽よ……」
「……?」
「関羽長生よ……。目覚められよ」
関羽が、寝床から起き上がると、そこに、見たこともない老人が立っていた。
彼は、長く立派な白い髯を蓄え、徳が高そうな老人で、杖を持っていた。
まさか、仙人か?
関羽は、自分の目を凝らす。
「そなたが、関羽長生であるな……」
「……何故、それがしの名をご存知なのですか?」
「そなたのことならば、なんでも知っておる」
「貴殿は、一体……?」
すると、彼は、穏やかに笑って答えた。
「わしは、南華仙人という者じゃ。人々は皆、わしを仙人と言うておる」
「これは……なんと! せ……仙人さまですか。仙人さまが、それがしに一体何用で……?」
南華仙人は、以前、若き日の張角にも、力を貸していたが、実はじき十八歳になる関羽の前にも、現れていたのである。
すると、南華仙人は、手を上にかざして、光を放った。
「!」
あまりにも眩い、青白い光に、関羽は思わず目を閉じた。
すると、その次の瞬間、その青白い光の中に、今まで見たこともないような、立派な大刀が姿を現したのである。
関羽は、少しの間、その大刀に見とれているのだった。
「関羽よ。そなたに、この『青龍偃月刀』を授けようぞ……」
「青龍……偃月刀?」
南華仙人の回りには、いつしか、青い光を放つ青龍が天駆ける。
「この青龍偃月刀は、四神であり、東と春を司る青龍と、あの空に浮かぶ、偉大な月の光の力を持つ大刀じゃ……」
「青龍と……月の光の力……」
「関羽よ。そなたは青龍と月を司る男だ……。その青龍の偉大な霊力を、善、そして義のために使い、太平の世を導くがよい……」
「……!」
関羽は、驚いて、南華仙人に尋ねた。
「南華仙人さま。何故それがしなのですか? それがしは、普通の人間の父母の元、生まれた者。それなのに何故……」
「!」
関羽は、ハッとして目を見開いた。
もう、そこはいつもの寝床であり、南華仙人の姿はなく、いつもの朝であった。
さすがの関羽も、辺りをきょろきょろと見回す。
「夢……で、あったのか……? ……しかし……」
そう。
そのしかし、だ。
南華仙人が授けてくれた、青龍偃月刀が、関羽の枕元にしっかりと置かれている。
「おお……、これはやはり、あのお方は偉大な仙人さまだったのだ……」
関羽は、青龍偃月刀を手に持つ。
ずっしりとした重さが、関羽の手に伝わる。
「これは重い……。この武器を使いこなせるよう、少し鍛錬せねばならぬな……」
関羽は、青龍偃月刀を握り締めた。
これが、青龍偃月刀が関羽に初めて持たれた瞬間であった……。
その時、呂澄が、関羽の様子を覗きに来た。
呂澄は、関羽に明るく声をかける。
「おうっ、おはよっす、関羽! 俺、あれから考えたけどさ。お前が喜びそうなのって、やっぱ本かなって思って!」
呂澄が、関羽の青龍偃月刀を見て、仰天して、目を白黒させた。
「関羽? うわっ、なんだ、その大刀は!?」
「うむ……これはだな……」
「お前、どうしたんだよ、それ? まさか、買ったのか!? なんて高そうな武器なんだ……!」
関羽は、どう説明したら良いのか、少々戸惑っていた。
しかし、呂澄なら分かってくれるだろうと、関羽は、全てを正直に話すことにした。
「これは、夕べ、南華仙人さまという、徳高い仙人さまから授けられたのだ」
「せっ、仙人さまだって!? そんなのが本当にいるのかよ……!?」
「本当だ……」
「マジかよ……」
呂澄は、関羽の瞳をしばらくじっと見ていた。
そして、微笑んだ。
「……信じるぜ、俺は、関羽のこと。やたら真面目なお前のことだ。お前は嘘つくことが大嫌いだし、こんなことで嘘つくわけねーもん」
「呂澄、かたじけない……」
関羽は、呂澄に頭を下げた。
「そーだそーだ。肝心なこと、忘れてた!」
呂澄は、関羽に風呂敷に包まれたものを手渡す。
「誕生日おめでとう! 関羽」
「おお、これは、例の書物であるな?」
「おう。お前が気に入るかどうかは分かんねーねどさ」
「うれしく思うぞ、呂澄。む……?」
布の結び目を解いた関羽は、細い目を見開いた。
それを見た呂澄も、怪訝そうな顔をした。
「どーした、関羽?」
「いや……まこと申し上げにくいことだが……」
「え。なんだよ、気に入らなかったんか?」
「いや、そうではない。しかしながら、実を言うとな。この書はもう、所持しておるのだ……」
「え〜! じゃあダブっちまったのか〜! あっちゃー、俺ってば、もっと調べりゃ良かったよ……」
呂澄は頭を掻いた。
「関羽は一番の友だちなのに、俺はなんも分かってなかったなあ〜……」
「いや! とても嬉しいぞ、呂澄。お主がわしのために、慣れておらぬであろう書店に入り、一生懸命選んでくれたのだと思うと……。それだけでわしは、心が満たされる思いなのだ」
「そっかあ? そう言ってくれっと嬉しいぜ。あ〜。しっかし、良かったよ。あれも買って……」
「あれも、とは?」
「へっへ〜! 実は関羽を脅かしてやろーと思ってさ。贈り物、本だけじゃねーんだよな〜。ほれ!」
呂澄は更に、関羽に小さな包みを手渡した。
「ほう……。早速だが、開けても良いのか?」
「もちろんだ! つーか開けてくれよ」
関羽は小さな包みを開け、細い目を見開いた。
「見ろよ、この玻璃玉の房飾り。俺とお揃いなんだぜ!」
「ほう……これはなんと美しい玉だ……」
紫の房飾りに付けられていたのは、黒地に鮮やかな青い七星文様のとんぼ玉であった。
関羽は、とんぼ玉の美しさに思わず目を奪われていた。
「渋い色合いで、俺にはどうかと思うけど、少なくとも関羽にはよく似合うよな!」
「これは、なんと美しい玉の房飾りを……。しかし、高かったのではないか?」
「そんなつまんねーこと、気にすんなって!」
「これはありがたい。呂澄。まことに感謝致すぞ」
「その大刀にでも付けとけよ。俺も、刀に付けるからさ」
「では、早速、そう致そう」
関羽は、青龍偃月刀に、呂澄は刀に、それぞれとんぼ玉の房飾りを付けた。
「へへへ……。親友の印っ! これで、俺と関羽は、一生友だちだぜ!」
無邪気に笑う呂澄を、関羽はとても優しい顔で見ていた。
「のう、呂澄……わしは、親友は親友でも、『心の友』と書き、『心友』と呼んでも構わぬか?」
「ん? 別にどっちでもいーよ! 関羽みてーなやつにそんな風に思われるなんて、俺は幸せもんだぜ! あはは〜!」
呂澄は、あまり深く考えず、屈託なく笑っていたが、『親友』と、『心友』では、意味がかなり違う。
その字の通り、『親友』は、親しい間柄の友だち、『心友』は、心の友なのだ。
当然ながら、関羽の言う『心友』の方が、相手を大切に思う意味が深い。
「それにしても、仙人さまからも誕生日の贈り物を頂くなんてな。やっぱり関羽は日頃の行いがいいんだな。それにカッコいい武器だよな! 俺にも持たせろよ」
「しかし、呂澄……」
「大丈夫だって! ふふん。こう見えても俺、力はなかなかあるんだぜ? って……げっ!?」
呂澄は、青龍偃月刀のあまりの重さに仰天した。
「なんだよ、この馬鹿重い武器は!? 関羽、お前こんなの、使えるのか!?」
「仙人さまが言われたのだ。使いこなしてみせる」
関羽の瞳には、既に、揺るぎない決意の色があった。
そして、十八歳になったばかりの関羽は、その日から、仕事の合間を縫って、毎日のように、青龍偃月刀で鍛錬をしていた。
「むんっ!」
ブンッ!
「はーっ!!」
ブンッ!!
あまりにも重いこの青龍偃月刀を使いこなすには、なかなか大変なものであったが、関羽は身体が大きく、力が強いため、すぐに難なく、青龍偃月刀を使いこなせるようになった。
そんな関羽をいつの間にか見ていた呂澄は、感心していた。
「すっげー……。さすがは関羽だな。あんなに馬鹿重い大刀を、もうそこまで振り回せるなんてさ!」
「おお、呂澄か」
「その大刀、お前にピッタリだよな! なんだか、でかくて、光が優しくて神々しくて、関羽にそっくりな武器だ」
「ところで、呂澄。お主、髭はどうした?」
「へへへ……。剃っちったよ。俺にはどうも、髭は合わないしさ。髭は関羽だけで十分だろうって思って」
呂澄は、つるつるになった顎を触りながら笑った。
「早く見たいなぁ。関羽がその髭、長く伸ばしたところ。綺麗なんだろうな〜! そしたら俺、櫛で梳かしてやるからさ! で、その後触っちゃうんだ」
「ははは……」
関羽と呂澄は、笑い合っていた。
|
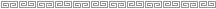 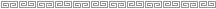 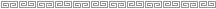 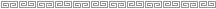
   
拍手ボタンを設置しました!\(^0^)/
お気軽にポチッと、どうぞ!(^^)v
|

